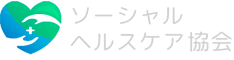今日は、上慎平著『弱さ考』をご紹介。能力主義や経済構造の問題をより掘り下げ、人間のあり方を問うという試みがなされています。著者自身、強くあろうとし続けて、立ち止まる機会を得たその経験を踏まえて、様々な文献をベースに論考されています。
「規範を守り、社会に求められる人間像の幅(レンジ)に自分をコントロールすることができる人は強く、それができない人は「弱い」。自己コントロールは現代に始まった事じゃないが、現代はその難易度が一気に上がっている」「自部にも他人にも、あまり理性を求めない」「非理性的に聞こえる「弱音」にも、ちゃんと居場所を与える」(今大事にしている方針)
私たちは「強くあれ」「自立せよ」「努力すれば報われる」という言葉を、子どもの頃から繰り返し聞かされて育ってきました。企業社会のなかで、家庭の中で、地域の中で、自らの価値を証明し続けることが当然のように求められてきたように思います。——とくに、働き盛りである30〜50代の私たちには、身に覚えのある感覚ではないでしょうか。本書では「時間を有意義に使おう」という考え方も、際限なく自分の価値を証明しなければならないという思い込みと関連すると指摘されています。
弱さを切り捨てる社会で、本当に人は生きていけるのか?
本書の中心にあるのは、「能力主義(メリトクラシー)」への批判的考察です。
能力主義とは、個人の努力や才能に応じて報酬や地位が与えられるという考え方です。努力した者が報われ、実力がある者がリーダーシップを担う。それは一見、民主的で開かれた社会の原則にも思えます。ですが本書では、能力主義が現代社会において、いかにして「差別と排除」の装置として機能しているかを論じています。能力があるとされる者にだけ「価値」が与えられ、そうでない者は「努力不足」や「自己責任」の名のもとに切り捨てられる。これは、平等を装った格差拡大の仕組みだというのです。しかもこの「能力」は、生まれや家庭環境、健康状態、ジェンダー、教育機会などに強く左右されるものであるにもかかわらず、「個人の資質」として矮小化されてしまう。社会的な構造的問題が、あたかも“本人のせい”であるかのように処理される——ここに最も鋭い批判があります。
「控え目に言って、成果はどこまでいっても不完全にしか評価できない。1つの成果には、数えきれないほど複数の原因が、つまり多くの人の貢献があるのだけど、その複雑さを人間の脳は認知できない。だから、便宜的に誰かに割り振っているだけなのだ」
これは、普段あまり考えないものの見方でした。人間には限界があるから、とりあえずだれかに成果の貢献者としての役割を割り振っているだけという。なんともいい加減で迷惑な話だ・・・。
「能力はそもそも環境によって決まるのだった」
「現代のに保温社会という環境にうまくハマらず、「能力が低い」と評価される不運な人を、金銭的にも、そして精神的にも孤立させない」
これはとても大切なことです。
■ 経済というシステムが人を「役立つか否か」で測るとき
井上氏は、現代経済の仕組みが「市場価値」を唯一の尺度にしてしまっていることも問題視します。私たちは知らず知らずのうちに、「自分が社会にどれだけの経済的貢献をしているか」で、自分の存在価値を測ろうとします。年収、役職、消費力、そして生産性。その結果、介護や保育、福祉、清掃といった、社会にとって不可欠な仕事——すなわち「エッセンシャルワーク」——に従事する人たちは、「役に立っている」のに評価されないという矛盾に晒されます。
「大事なことだが、「社会的価値の高さ」と「給料の高さ」はなんの関係もない。その仕事がどれだけ世の中を支えてるかは、給料に反映されない。給料は阻利率のたかさや希少性など他の要素によって決まる。労働市場の大きな欠点の1つはここにある(中略)だからこそ市場任せにしないことが大切なんじゃあいだろうか。仕事の社会的価値と給料は比例しない。そして市場原理に任せれば、一度に多くの人を相手にできないエッセンシャルワーカーの給料は低くなる傾向にある。ならば、市場「以外」の要素によって補われたほうがいい。」
コロナ禍でそれが一時的に可視化されましたが、危機が過ぎると元の「不可視」の状態に戻った現実を、私たちは知っています。つまり、今の経済構造は、人間の尊厳や労働の意味を「貨幣的価値」によってしか扱えない状態に陥っているといえます。
■ 弱さは他者の問題ではなく、私たち自身のもの
『弱さ考』というタイトルに、最初、私自身もどこか違和感を覚えました。「弱さ」と聞くと、「誰か他人のこと」「支援すべき対象」といったイメージが先に立ってしまう。しかし、本書を読み進めるうちに、その認識そのものが問い直されていきます。
井上氏は、弱さとは「属性」ではなく「状態」であり、もっと言えば「関係性」だと言います。誰もが健康や能力を失う可能性を持ち、誰もが他者に依存せずには生きられない。つまり、弱さは他人の話ではなく、私たち一人ひとりが生きる現実そのものなのです。たとえば、病気になったとき、親の介護が始まったとき、職を失ったとき。あるいは、精神的に消耗し、もう「普通に働けない」と感じたとき。そうした瞬間に、社会の構造は急に冷たくなります。
そのとき初めて、人は「弱さ」が排除される社会のあり方に直面することになるのだといいます。
■ 「共に生きる」という、人間らしさの再発見
本書の終盤で提示するのは、「弱さを前提とした社会」への転換です。競争ではなく協働、効率ではなく関係性、優秀さではなく共感——それは経済合理性とは相容れないかもしれません。しかし、だからこそ私たちが今、立ち止まって考え直すべき方向性でもあります。
本書を読むと、自分がどれほど「強くあること」に縛られているか?ということを振り返らされます。「支えるー支えられる」という単純な関係ではなく、「共に揺らぎながら、それでも関係を築いていく」という人間のあり方。それが、井上氏の描くビジョンであり、本書が読者に投げかける深い問いなのです。「弱さ」に違和感を覚えるとしたら、それは、私たち自身がその弱さを抱え込んで生きてきた証かもしれませんん。
最後にもう1つご紹介しましょう。日本は「社会的原理」(社会秩序を成り立たせる道徳心を、他者との共感を通じて養うことを重視する)、アメリカの「経済的原理」(比較検討し最も早く確実な手段を選択し目的を達成すること」により教育が組み立てられたというものです。日本では「この社会があなたに何を求めるか」ー「自分の意見を押し通さない」「異なる立場から考える」思考スタイル。「他者の心情の読み解き」「共感」。これらが教育の中で刷り込まれていくといいます。日本的な感性は、「おのずから」の感性が求められる(コントロールできないものとして世界をとらえる)そのため、ビジネスのなかで、自分でコントロールして強い人間になろうとすると、これままで教えられてきた思考スタイルとも全く違ってしまいます。そこで、ストレスがかかるのかもしれません。アメリカが重んじるのは「目的の達成」。この点で大きな違いがあるというのです。
本書は様々な文献を検索して、そこから論じる手法を用いておられます。
お時間のあるかたは、一度読んでみて頂ければと思います。
「市場価値と、自分そのものの価値とは全く関係がない」