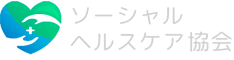最近、ドキュメンタリー映画づいています。この映画は、震災と原発事故から13年。福島ー原発による被害を受けた一部の地域の人の今を切り取った110分。
メンタルクリニックの院長、蟻塚亮二医師は、連日多くの患者たちと向き合い、その声に耳を傾ける。連携するNPOこころのケアセンターの米倉一磨さんも、こころの不調を訴える利用者たちの自宅訪問を重ねるなど日々、奔走していた。 津波で夫が行方不明のままの女性、原発事故による避難生活中に息子を自死で失い自殺未遂を繰り返す男性、避難生活が長引く中、妻が認知症になった夫婦など、患者や利用者たちのおかれた状況には震災と原発事故の影響が色濃くにじむ。(映画の紹介文より引用)
原発事故で一家離散になり、家族の形が崩壊し、時には自らいのちを絶ち、生きていても希望を抱けず、今そしてこれからに目を向けられずに、2011年3月でときが止まったままの人びとが、恐らくとてもたくさんいるのだと思います。映画に登場するのはそのうちほんの数人。
この映画では意図して、東京オリンピックの聖火リレーの福島での様子、菅首相(当時)の「明かりが見える」「勢いがついてきた」などの言葉、岸田総理の「復興が進んで住民が戻ってきている」といった言葉が随所に織り込まれています。どれもこれも、違和感しか覚えません。いかにして事故を風化させ、忘却し、前だけを見て進むか、その果てには原発再稼働や原子力エネルギーの推進やアメリカの核兵器の容認、もしかすると憲法改正をも包含するストーリーを展開しているかのよう。この12年、「つくりものの復興」を行って演じて来たかのように見えてしまいます。
映画は限られた「個」をクローズアップしつつも、この人たちが暮らす福島という地域性や、日本における原子力エネルギー活用や原発プラント誘致の歴史を、時間軸を戦前にまで広げて俯瞰し、この地で何が起こってきたのか、人びとの健康に影響してきた外部の要素を端的にまとめ、社会に訴えかけてきます。映画が伝えたいことは、きっとこういうこと。。
自己責任では済まされないことである。

「本当は健康でいたい」 と言いながらも、過去で立ち止まったまま動けない男性。アルコール依存症になり、健康を害していく男性。
避難先の新潟に妻子を残し、原発事故後処理の仕事で収入を得るために単身福島に赴任していた男性。息子が新潟で自死し、離婚となり、悔いて、自分を責めて、体を壊していく。
原発事故ですべて失い、補助金もついに打ち切りとなり生計を立てられなくなり、生活が破綻し、健康被害へとつながっていく。その先のセーフティネットが、この映画に登場する精神科医や精神科訪問看護ステーションの看護師だったり、こころのケアセンターだったり ー医療保険、介護保険、自立支援医療などの公費は投じられているものの、基本「自助」である。 自力で復興してね、トラウマにまでは責任負いませんよ、と。
この映画は舞台を沖縄にも移して、共通する課題 「遅延性PTSD」 について問題提議しています。今になって、幼少時終戦を迎えたときに負ったPTSD症状が出現する人たちがいるということ。福島でも、10年経った後になり、突然発症している人が絶えないという。
沖縄と福島に共通する背景ーそれは、貧しい地域であるということ。国策に翻弄されてきたということ。
ーアメリカが原子力兵器の開発を推進するうえで、国際的に原子力のイメージをよくしなければならないと考えた。原子爆弾投下国である日本で、原子力エネルギーを受け入れたならば、原子力への国際的な理解(容認)が促進するであろうという下心から、原発を日本につくることを推奨したー
人が少なく、これという産業がないー
つまり危険性がある前提で建設する原発周辺地域には人や企業が集まらないことが望ましい。人が少なければ、(反感感情が集結して)原発設立反対運動などが起こらないであろう といったことを推測して、この立地を選んだといいます。大学で教鞭をとっていた時、福島で起こったこと(大学生はみな当時小学生で事実をよくしらない)、そして放射線や放射線防護について、現存被ばく状況が続く地域での保健師の役割についてetc.、授業と演習を行っていました。原発を推進してきた歴史についても紹介していたのですが、こうした歴史から福島の人の健康を考えていかなければならないと、映画を見て改めて思いました。


(ロシアのウクライナ進軍におけるプロパガンダと、日本で行われてきたこういったプロパガンダに違いはあるの?日本でもまだプロパガンダは随所で行われています)
現存被ばく状況における看護・・・それ以前に、当時「原発が爆発して死ぬかもしれない」という恐怖の体験をしたこと、その後、わけもわからず集団で転々と避難させられたこと・・このことで負った心の傷というものは、放射性物質が半減しようとも、心に深い爪痕を残してしまっているのだということを、映画を見て考えさせられました。
昨今、自然災害が毎年毎年多発し、能登半島の復旧復興もままならないなか、各地で河川の氾濫が起こっています。避難住宅に暮らせる期間は限られ補助は遅かれ早かれ打ち切られる。その補助を受ける手続きも大変な労力が必要でままならない人もいるでしょう。その後人びとがどうなったのかは、誰にもわからない。
この映画により、福島のことだけでなく、地方自治体で保健師として仕事をしていた時に出会った、たくさんの困難を抱えた人たちの顔を思い出させられました。その人が生きよう、と一歩踏み出せるきっかけはどこにあるかわかりません。それをじっと見守り続ける人たちが必要なのです・・・。
保健師としてもこの映画の看護師さんのように多くの人に関わり、また、研究者としてそれなりに多くの人たちにインタビューをしてきました。一人ひとりの語りに圧倒され、この現状をいかに多くの人に知ってもらいたいと思っても、研究でさえそれは、個人情報の保護や倫理的配慮からオープンにできない。個人が特定されないようにしなければならず、結果を公表する段階になると、その語りの威力というものがどうしても小さくなってしまう。ドキュメンタリー映画がもつ生の映像と声の圧倒的な力/影響力を思いました。それだけに気をつけなければ、一部を誇張してしまったり、監督が描く「ストーリー」がすべてになり、真実が偏って描写されかねません。ドキュメンタリーは見る側もそこに気をつけなければなりません・・・それでも、この映画は多くの人に見てもらいたいと思いました。
最後に奄美の海を・・・。沖縄の海も、相馬の海も…海は変わらずに在る